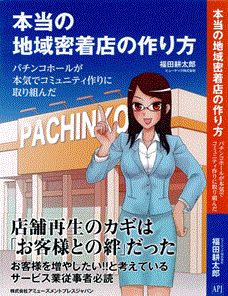ブログ
経営のヒントになりそうに思ったこと
■店舗運営で最も大事なことは「飽きさせない」こと!
コンビニのセブンイレブンを展開するセブン&アイホールディングスは、 イトーヨーカ堂を含めたスーパーマーケット事業の立て直しを模索しています。 読売新聞は、セブン&アイ名誉顧問であり、日本のセブンイレブンを作った鈴木敏文さんに 小売業の経営についてインタビューをしていました。 4月20日その記事が載っていたのですが、タイトルは「消費者飽きさせない」となっていました。
「70年代にセブンイレブンを作る前、日本には小規模な商店がたくさんあったが、品ぞろえができていなかった。 それなのに小規模な商店だからダメなんだという考えが根強かった。(読売新聞朝刊より)」
パチンコ業界でもよくある発想ですね。
小規模だからダメなんだ。
大きな規模の店舗には勝てない。
という話をしている人は結構いました。
鈴木敏文さんは、店舗の大きさではなくて品揃え、P業界で言えば、台の機種揃えが本質的な問題なんだ、
と言っているということですね。
要するにどんなに大規模店舗でもダメ台しかなければ、1000台の店であろうが2000台の店であろうが流行らない。
逆に地域の人が打ちたいと思っている機種揃えをすれば、お客様は店舗に来てくれるということですね。
鈴木敏文さんの著書を読むと、多くの人が表面的な理解をしていることに、本質的な見方を提示してくるので、
経営のプロと言う感じがします。
そして、読売新聞の記事は、品揃えの話から飽きの話へと進んでいきます。 品揃えの大切さとは、品揃えをすることではなく、お客様を飽きさせないことだと指摘されています。 お客様のニーズやウォンツを捉え、きっちり品揃えしたから安心と思うと足をすくわれるということですね。 その理由は、どんな品揃えをしたとしても、変化が無ければ、お客様は必ず飽きてくる。 お客様は飽きてくると店に来なくなる。
「だから小売業でもっとも大事なことは、常に目先を変えて消費者を飽きさせないようにすることだ。」と書かれています。
小売業にとっても、パチンコホール業にとっても、一番大切なことは何かといえば、お客様に来店してもらうことです。 あなたは飽きてしまった店舗に行きたいでしょうか? 別に行きたくないでしょう。 もし足を運ぶとしてもそれは積極的なものではないはずです。 もし、飽きさせない店舗が近くにできたら、そちらに行くのではないでしょうか?
店舗運営と言うことで、いろいろなことをしていると思います。 新台入替や装飾変更、景品イベント等いろいろです。 それは何のためにしているのですか?と問われた時に、最終的には来店してもらうためとなると思います。 来店してもらうために大切なことは”飽きさせない”ということですから、 全ての施策にこの要素を含ませることが大切なのではないでしょうか。
地域密着型ホールやコミュニティホールに取り組んだとしても、 その活動を店舗がやり続けたとしても、お客様に飽きられてしまえばどうなるでしょう。 お客様評価はゼロになるのではないでしょか。 お客様評価ゼロの活動をやり続けて、地域密着型ホールやコミュニティホールはできるはずはありません。 そんなことをやっても店舗を評価しないし、それがあるから来店したいとも思わないからです。 その活動はただの自己満足になってしまっているということですね。 自分たちは一生懸命やっているのになぜかお客様が評価してくれない。 その理由はこれかもしれませんね。
お客様が来ない、だんだん減ってきている。
地域密着型ホールやコミュニティホールに取り組んでいるのにパットしない。
もしかしたら、鈴木敏文さんが最も大事なことと指摘している「お客様を飽きさせない」という部分が、
疎かになっているのかもしれませんね。
今している施策の中に「お客様を飽きさせない」ために工夫をどのように組み込んでいるか、
一度チェックしてみることをおススメします。
・・・ 👆目次
作成日:
■「春の熱中症」予防キャンペーンで気遣いをする!
最近、ニュースなどを見ていると、「春の熱中症」という言葉が目につきます。
2024年の春は、平年よりも気温が高い傾向にあるようです。
気象庁の1か月予報によると、4月17日頃からは10年に1度のレベルで高温が予想されており、
全国的に暑さ対策が必要とされています。
この傾向は続くので、行楽に行かれる方や畑仕事や建設現場など野外の仕事をされている方に、
注意喚起をするのがおススメです。

参考資料:気象庁 | 季節予報解説資料
お客様の好感度を上げる方法の一つは気遣いです。
今年の気温傾向が出ているので、お客様に元気でいてもらうために早めに気遣いをして、好感度上げてください。
「いつも、ありがとうございます。」
とニコッと笑って言うのと、
「いつも、ありがとうございます。
今年の春は10年に1度の高温になると予報がでているので、熱中症にお気をつけください。」
とニコッと笑って言うのとでは、どちらが地域密着的、コミュニティホール的でしょうか?
言うまでもないと思います。
特に気温の変化に対応しにくい高齢者の方などには、体調不良になる可能性が高いので要注意です。
最近、身体の調子が悪くて来れない高齢者のお客様はいらっしゃいませんか?
毎日のように来ていた気心のしれた常連さんが、ある日ぱったり来なくなる。
それは他店へ移動したというより、体調不良の可能性が高いと思います。
常連さんを一人失うということは、月に1回来るライトユーザーを20人失うのと同じなので、
体調管理ができるように店舗がフォローするのは、ある意味当然ではないでしょうか。
そんなことを言ってもスタッフが不足していて忙しい、
あるいはスタッフのレベルがそこまで達していないという店舗もあるかもしれません。
その時はスタッフが頑張るのではなく、補助的なツールを用意すれば問題ないでしょう。
例えば、サービスカウンターの上に、健康情報として「気象庁発!春の熱中症に要注意!」などとミニのぼり旗や札に書いて、
「ありがとございます。お気を付けください」と、それを指しながら言えば大丈夫でしょう。
もう少しイベント的にやるなら、
「GW前の特別企画、春の熱中症予防キャンペーン」などをするのも一つです。
店内に日本気象協会が推奨しているポスターを貼って、熱中症グッズを景品(賞品)として並べる。
熱中症対策グッズと言えば、
・せんす、うちわ、携帯扇風機
・日傘、帽子
・飴などの塩分タブレット
・水やスポーツドリンク
などですね。
手軽にやるなら、熱中症予防のための飴を配布するのが一番簡単ですね。
端玉景品にも、その飴を用意しておけば、試食も兼ねることができます。
景品の販売も思い込みはダメですよね。 お客様本人が使うのを前提として、飴などを勧めてしまうケースですね。 お客様自身じゃなくても、子供さんやお孫さんがいるかもしれません。 これまでの会話の中で、お孫さんがいるなら、「お孫さんのためにどうでしょうか?」と言えば、 自分の話を覚えてくれていたと、喜んでもらえると思います。
それから、駐車場の子供の放置にも気を配る必要があるでしょう。
日本自動車連盟(JAF)が2019年5月8日に屋外駐車場で行った実験では、
外気温が23.3℃〜24.4℃ぐらいだったのですが、直射日光の当たる場所に駐車した車は、
計測開始時25℃だった車内温度が約2時間後に、
軽ワゴン車で39.9℃、大型SUVで46.5℃を観測しています。
真夏には、店舗でも駐車場の見回りをされているところも多いと思います。
今年は、そろそろ晴れた日などには見回りをした方が良いかもしれません。
お天気がらみの気遣いは、一番自然でやりやすと思います。 地域密着型、コミュニティホール型を目指しているなら、 「春の熱中症」予防で、お客様との関係づくりをしてはいかがでしょうか?
最後に、一度「春の熱中症」予防のおススメをした人に、
全く初めてのようにまた「春の熱中症」予防のおススメをするのは厳禁です。
それは相手のことを覚えていないサインになってしまうからです。
端的に言えば、お客様軽視ですね。
関係づくりの真逆です。
頑張って関係づくり企画をしているのに、お客様との関係が築けない店舗によくある光景です。
労多くして成果なしは悲しいですね。
くれぐれもスタッフには、朝礼等でお客様の顔を覚えて案内する重要性を必ず伝えておきましょう。
・・・ 👆目次
作成日:
■JR東海の丹羽社長の発言から施策検証を考える!
4月17日にJR東海は、東海道新幹線に「完全個室」のシートをつくると発表しました。 ご存知のように東海道新幹線には、一般自由席シート、一般予約席シート、グリーンシートの3種類がありますが、それに加えて完全個室シートという新たな座席を用意するということです。
今回計画している個室は、完全個室ということなので、高いプライベート感があり、セキュリティ環境の強化されるものになっているようです。
そして部屋には専用の Wi-Fiがあり、座席はレッグレスト付きのリクライニングシートとなっています。
照明も明るさを個別調整可能なものにし、空調の風量や車内放送の音量の調節機能も付けるようです。
想定している利用者は、オンライン等での打合せを気兼ねなく行いたいビジネスパーソンやプライバシーを重視されるお客様、周囲を気にせずゆっくりとしたいお客様です。
新幹線に乗ってゆったりと移動したいという人は多いはずです。 そのためのグリーン車ということですが、グリーン車も座席が満席状態になると、結構ストレスがたまるものです。 快適な空間のためならお金をいくら払ってもいいという人は確かにいますので、ニーズはあると思います。 価格はいくらになるかはわかりませんが、飛行機のファーストクラスのような感じですね。 2026年度からN700S車両で導入されていくようです。
この完全個室の発表で私が注目したのは、丹羽俊介社長がこの完全個室シート設置の目的を、
売上アップのためではなく、多様なニーズへの対応のためと言われたことです。
この完全個室が成功したか失敗したかは、多様なニーズを満たしやかどうかで判断されるということです。
逆に言えば、これよって売上が上がったとしても、多様なニーズへの対応になっていなければ失敗だということです。
リニア新幹線はおそらく時間の問題でしょう。
JR東海は、新幹線に対して移動という単純なニーズから、
それ以外の様々なニーズに対してどう対応していくかを、
今後の経営課題としてとらえているのかもしれません。
そういう中での挑戦的な取り込みと位置付けているのでしょう。
よくある失敗とはこんな感じですね。
例えば、このケースで言えば、完全個室シートを導入したけれど、多様なニーズには応えられなかった。
しかし、売上は3%アップした。
それで良かった、良かったと思ってそのままにしていたら、
ある日を境としてお客様の多様なニーズに応えられず、売上が減少し始める、
慌てて対策を打つが減収減益になってしまった。
傍から見ると間が抜けているように見えるかもしれません。
しかし、何のためにやっているかをあやふやにしているとよく起こる現象です。
パチンコ業界で言えば、例えばお客様に社会貢献を意識している店舗というイメージをもってもらうためにペットボトルのキャップ回収(エコキャップ運動)を行っていたが、お客様には店舗が社会貢献をしていると意識されていない。
店舗自体も当初の目的を忘れて、ただキャップを集めている。
ワゴンサービスのメニューを強化したが、お客様ロイヤリティ向上のためか、遊技時間延長のためか、来店動機をつくるためか、目的があやふやなまま実施した。
とりあえず、ワゴンサービスの売上が上がったのでよしとしたが、相変わらず稼働の低下が続いている。
などでしょうか。
目的が不鮮明になると問題が何かかわからず、施策の検証ができない。
あるいは間違った検証をしてしまう。
この状態は、いろいろと手を打つが、必要な経営課題が解決できないという「頑張っても成果がでない世界」に迷い込むことになります。
余計なおせっかいかもしれませんが、JR東海さんのように、事前に目的や成果を明確にして、施策に取り組むことをおススメします。
参考資料:東海道新幹線への個室の導入について
・・・ 👆目次
作成日:
■セキュリティ・クリアランス制度を意識向上に使う!
今月の17日から参院本会議で『セキュリティ・クリアランス制度』の審議が始まりました。 この制度は経済安全保障分野の機密情報を取り扱う人を政府が認定する制度です。 背景は国際情勢の不安定化とともに、世界はともに競走しながら発展していくという考え方から、 自国に不利を招く恐れがある国に対しては距離をおくという考え方に変わってきています。
端的に言えば、敵対する可能性のある国が発展すると、自国に害を及ぼすという考え方が、
ロシアのウクライナ侵攻以降は主流になってきているのではないでしょうか。
それまでは、経済的に協力関係を密にすると、相手を軍事攻撃すれば自国の産業も痛む(不利益を被る)ので、
そんなバカなことはしないという思い込みが前提でした。
なので各国のグローバル化イコール世界平和という幻想をみていたのです。
これは、グローバル化を進めて儲けようとしている大企業にとっては非常に都合が良いので大賛成、
政府の後押しを積極的にしていました。
ところがロシアが想定外の暴挙にでたことで、経済協力関係にあっても平和が守られないことが証明されてしまいました。
このため敵対が予想される国に対して、何でもOKはマズイということになり、特に軍事に転用できる最先端の研究や技術の情報、
サイバー対策、先端技術のサプライチェーンに関する情報は規制がすべきという考え方を日本も取り入れることになったというわけです。
法案は、漏洩すると安全保障に支障を与える恐れがある政府保有の情報を「重要経済安保」とし、 資格がないとそれらの情報を取り扱くことができないとするものです。 この資格の特徴の一つが、身辺調査です。 調査事項は、重要経済基盤毀損活動との関係、犯罪歴、情報の取扱いに係る非違(違法)の経歴、薬物の濫用、精神疾患、飲酒についての節度、信用状態などが含まれます。 審議では、国民民主党の竹詰仁さんが、調査項目に「ハニートラップ」がないと問題を指摘したのに対し、 高市経済安保大臣は、「調査の対象」となると答弁する場面もありました。 ちなみにハニートラップとは、性的関係を利用して情報を引き出すことを言います。
パチンコ店も漏れるとたいへんなことになる機密性の高い情報を取り扱っている業種の1つだと思います。
経済犯罪実態調査2020によると、日本企業の経済犯罪被害に遭った場合、
不正行為に関与した主犯格は、組織の内部者が53%、組織の外部者が44%であることが示されています。
お客様に安心して遊技をしてもらうためには、店舗の情報の流出はもってのほかです。
店舗の幹部のセキュリティ意識は高いと思いますが、そういう人をターゲットにしている犯罪者がいるのも確かです。
しかしながら、こういう問題はきっかけがないと話題にしにくいものです。
今回審議入りした『セキュリティ・クリアランス制度』を取り上げて、
情報管理の大切さ、情報管理者としての危機管理などを話し合ってみるのも、
役職者のさらなる意識向上につながるのではないでしょうか。
・・・ 👆目次
作成日:
■お客様にスタッフの接客力上達を知らせる価値!
この季節は花粉に黄砂が気になります。 私にとって目薬は必須のアイテムなので、近くのドラッグストアに買いに行きました。 会計を頼んで、ふとスタッフの胸元を見ると「接客優秀者」という名札に気づきました。
名札について尋ねると、覆面調査が定期的に行われており、その時評価が良かったので、 もらったということです。 確かにそのスタッフは愛想がよく、良い感じがしていました。 私は「おめでとう。良かったね。」と言ってその店を後にしました。
私が思ったのは、このドラッグストアは会社の方針として、接客を重視しているということと、
名札のようなもので評価結果をお客様に知らせることは、悪くない施策だと思いました。
接客上達すれば時給を上げる店舗もありますが、それだけだと接客が向上していることはお客様に直接伝わりません。
実際、スタッフが頑張って接客力を上げたとしても、お客様はなかなか気づかないものです。
しかし、このように目に見える形にしてあると、お客様がスタッフの能力向上に気づくことができますし、好感を持てるスタッフには、声を掛けることもできます。
こういう工夫は、コミュニティホール作りの十分条件のひとつである”顧客満足に対する努力”を知ってもらうことにつながります。
また、会話のネタにもなり、スタッフが名前も覚えてもらう可能性も高まります。
お客様を巻き込み、スタッフの接客投票によって、接客PRとスタッフの名前を憶えてもらう手法も悪くはありませんが、 店舗がスタッフの評価をお客様に見える形にするのも悪くないと思いました。
・・・ 👆目次
作成日:
■アストンマーチンの販売発想を取り込む!
今月5日に銀座に英国車のアストンマーティンのシュールームができました。 場所は有楽町のザ・ペニンシュラ東京の1回です。 アストンマーティンと言えば、ジェームズボンドお気に入りのクルマとして有名です。
ニュース番組WBSで、銀座に豪華なショールームを作った動機について取材をしていましたが、
「高級ブティックで服を買うように、街を歩きながら車を選んで欲しかった」からだそうです。
ぶらっと立ち寄って買ってねということですね。
価格は「DBX707」で3290万円~だそうです。
売れるのでしょうか?
ちなみに2023年は世界の中で東京の販売台数が一番だったようです。

このアストンマーティンのトップがWBSのインタビューで語っていた言葉が印象に残りました。
「いつも言っているが、我々が売っているのはクルマではなく、”夢”である」
という言葉です。
アストンマーティンに乗ることで、夢見ていた生活をエンジョイすることができる。
ボンドガールのような彼女を乗せてデートをすることかもしれませんし、
百貨店やホテルでVIP対応をしてもらえるかもしれません。
また、道行く人が羨望のまなざしで見てくれるのかもしれません。
とにかく、何らかの夢をかなえる手段になるということですね。
3290万円で夢が叶うのであれば、お買い得と言えるのかもしれません。
夢を売るための店舗はどうあるべきか、夢を売るための接客サービスはどうあるべきか、
と考えて店舗づくり、接客サービス設計をしていく場合と。
クルマを売るための店舗はどうあるべきか、クルマを売るための接客サービスはどうあるべきか、
と考えて店舗づくり、接客サービス設計をしていく場合。
どちらも同じ店舗、同じ接客サービスになるでしょうか?
多くの人はならないと思うのではないでしょうか。
目的が違うと手段が違ってくることは当たり前ですよね。
何を売るかという目的が先で、それに応じる手段が後ということになります。
ところでみなさんは店舗では、お客様にどのようなモノを売っているのでしょうか?
単に遊技台体験を売っている店舗もあると思います。
ワクワク・ドキドキ体験を売っている店舗や勝ち体験を売っている店舗もあるでしょう。
安心安全な遊び体験を売っている店舗もあるかもしれません。
コミュニティホールを目指すところは、
コミュニティや第三の居場所を売っているのではないでしょうか。
遊技体験を通して、何を売っているかを明確にすることで、
今の店舗設備や運営、接客サービスの改善のヒントに気づくのではなでしょうか。
・・・ 👆目次
作成日:
■大型連休企画にお客様情報を活用しよう!
ニュースで、新幹線のゴールデンウィークにおける予約状況が報道されました。
JR各社は、大型連休を含む11日間(4月26日から5月6日まで)の新幹線の予約状況をまとめ発表しました。
それによりますと、4月11日の時点での指定席の予約席数は、約238万席で、予約のピークは、下りが5月3日、上りが5月6日となっているそうです。
去年と比べると17%増え、新型コロナの感染拡大前の2018年と比べても9%増加したということです。
予約が増えた理由は、東海道・山陽新幹線の「のぞみ」で、すべて指定席としていることや、3月に北陸新幹線が延伸開業したこと影響などが挙げられていました。
ゴールデンウィークが近づいてきています。
みなさんの店舗では、大型連休中の企画をすでに考え済みだと思います。

ところで、みなさんは大型連休中のお客様の動きをどれくらい把握していますでしょうか?
連休中に旅行に行く方もいると思います。
あるいは、日頃家族サービスをしていないので、この期間に子供たちをいろいろなところに連れていく計画を立てている方もいるのではないでしょうか。
お客様自身が子供たちを喜ばそうと主体的に考えている人もいれば、
奥さんからきつく子供の日はしっかりサービスをするように言われている人もいるかもしれません。
中には、お父さんやお母さんを誘って近場の公園や観光地を行こうとしている人もいるのはないでしょうか。
また、息子や娘が都心から帰ってくるのを心待ちにしている人もいるのではないでしょうか。
逆に単身赴任しているので、この時期は家族のいる家に帰る人もいるでしょう。
一方、この大型連休中に畑仕事をしてしまいたいと思っている人もいると思います。
もちろん、この大型連休はフルにパチンコ店へ行き、遊ぶ計画を立てている人もいるでしょう。

コミュニティホール作りの十分条件として、第五番目に”お客様を知る”ということを取り上げています。
その重要性は、お客様を知ることでお客様の好感度を上げるいろいろな企画をつくることができるからです。
例えば、旅行に行く人が多ければ、大型連休前に旅行に役立つ旅グッズを紹介したり、ポイント景品で揃える企画が考えられます。
家族サービスを考えている人が多ければ、家族サービス企画として、移動中のお菓子を端玉景品やポイント景品で揃えることできます。
家族の元へ帰る人が多いなら、連休前に地域のおススメ商品企画をすることもできるでしょう。
また、畑仕事を予定しているなら、疲れをとるための入浴剤の提案や疲労回復に役立つ栄養ドリンク等をおススメする企画も考えられます。
そして、お客様に対して「連休中に○○をすると言われていたので、是非、△△のときはご来店下さい」と言えれば、相手のニーズやウォンツを踏まえた提案なので関係が深まると思います。
何の理由もなく、ただの思いつきで、とりあえず『沖縄物産展』を企画したとしましょう。
ホールスタッフから「ゴールデンウィークに『沖縄物産展』を企画しました。是非来て下さい。」と言われて、お客様は悪い気はしないと思いますが、「なぜ、沖縄物産展?」となったとき、店が考えた客寄せ企画としか言いようがありません。
自店のコミュニティホールのレベルを上げたいということであれば、蓄積した関係を活かして、お客様情報の収集を行い、それを基にした企画を考えることが大切です。
こういう相手のことを配慮した企画を考えることができると、お客様は自分たちの会話を大切にしていると感じ、このホールは他の店舗と違うと感じられるようになります。
あなたは、いろいろな会話をしても、その会話を活かさない店舗に愛着や温かみを感じるでしょうか?
お客様から見ると、それは双方向の関係では無く、コミュニティを感じることはできません。
コミュニティゼロ企画です。
これは、コミュニティを志向していない店舗と同じです。
もし、ゴールデンウィークのお客様の動きが分かっていないということであれば、 すぐにでもアンケートなどをとり、お客様情報を収集することをおススメします。 その情報を基に今の企画の見直しやブラッシュアップできると思います。 また、新たなアイデアも浮かぶのではないでしょうか。 何よりも、お客様を知った上での来店おススメトークは、説得力が違ってきます。
最後に、お客様に連休中毎日来てくださいと考えるよりも、 連休中にパチンコ店以外の場所に行って、家族サービスや気分転換されてはいかがですか、と考えたほうが、業界のイメージアップになりますし、何より健全なパチンコユーザーの育成になると思います。 来店回数が減ってしまうと心配する人もいるかもしれませんが、顧客シェアをアップすることで、ある程度カバーできます。 心配はいらないと思います。
・・・ 👆目次
作成日:
■中田カウスさんの松本人志問題の判断視点に学ぶ!
検索サイトを開くと偶然、大阪芸人のドンと言われている漫才師の中田カウスさんが、 松本人志問題についてフライデーに語ったという話のタイトルが目に入りました。
「松本はアウトやて。本当に客、素人に手をつけたのであれば」
いろいろな芸能人が松本人志を擁護するような言動をしてます。 論点は、合意なしかありかに集約されているように思います。 合意がればセーフ。合意がなければアウト。 合意があれば”問題無し”ということですね。
しかし、中田カウスさんの判断視点はそうではありませんでした。
松本人志さんが、素人に手を出したかどうかを問題としています。
これは芸人としてのあるべき姿に照らして、松本人志さんの行動に対して問題ありとしています。
これまでの合意のある行為、合意のない行為以前に、行為(素人さんに手を出した)があったことでダメだという主張です。
FRIDAYデジタルの文章を引用させてもらうと
「お客を大事にせなあかん、という芸人の意識があったらそういう気分にならへん。松本に師匠がいたら会社の処分以前に破門になってたと思う。
芸人なら、相手を気遣うということが大事なんですよ。素人の女の子と揉(も)める。これはもう最低やわ」
というような感じです。
私はこの記事を読んで、中田カウスさんは、日本の芸能界のあるべき姿という大局を考えてる人であり、
芸人としての「矜持(きょうじ)」を持っている人だと思いました。
「矜持」という言葉は、自信、自負、誇り、プライドを持つという意味だけでなく、自分をコントロールする、自分を抑える、自分をつつしむという意味も含まれています。
芸人としてお客様を笑わせる、喜ばせる、そのためにあらゆる努力をする。
その結果として富や人気が手に入るかもしれない。
しかし、どんな富が入っても人気が出たとしても、芸人としてあるべきルールを守ることが芸人を芸人たらしめていると考えているのだと思います。
富や人気が出たからといって、やりたい放題、挙句の果てにお客様にも手を付ける。
そこには”芸”を神聖視するものはなく、だた”芸”を自分の欲望の達成手段として活用していく道具と考えている。
これはこれまで”芸”を磨いて、その価値を高めてきた先人の顔に泥を塗る行為と見えているのではないでしょうか。
吉本興業には多くの芸人の卵がいます。 彼らが育って人気が出てくれば、その人気を利用してお客様としてきた女の子に手を出す。 挙句の果てにトラブルを起こす。 これは望ましい姿でしょうか。 「人間だから増長することもあるさ、仕方がない」と思えるでしょうか。 そういう芸人を尊敬できるでしょうか? 日本の顔として、メディアへの露出、親善大使、観光大使がつとまるでしょうか? そう考えると中田カウスさんの発言は、非常に明快で、松本人志問題は裁判以前の問題であると感じました。
中田カウスさんの話から学んだのは、
自分の仕事に対して「矜持」を持つことの大切さです。
矜持を持つことによって、仕事にやりがいを感じ、自分を律することができる。
もちろん、自分の所属する業界や会社が良い業界、良い会社であることが必須です。
ではパチンコ業界はどうあれば矜持を持てる業界になるのでしょうか。
また矜持を持ち続けられるのでしょうか。
自社はどうあれば矜持を持てる業界になるのでしょうか。
また矜持を持ち続けられるのでしょうか。
たまにはこういう話を会議でするのも悪くないのではないでしょうか。
参考資料:中田カウスが松本人志騒動に言及
・・・ 👆目次
作成日:
■キリン『晴れ風』の社会貢献を応援する!
キリンビールの『晴れ風』はもう飲みましたか? キリンが17年ぶりに投入した新ブランドです。 麦芽100%で、過度な酸味を押さえ、飲みごたえと飲みやすさを両立しています。
キリンが新しいブランドを投入した背景は、昨年10月の酒税法の改正が一因です。 2023年にはビールがビール類販売量の50%を超えました。 予想では、さらにビールの割合は増えていくと見ています。 ビールが少し安くなったということで、消費者の関心が発泡酒や第三のビールから、 ビールへと戻ってきているんですね。
新商品ということで、ホールでも端玉景品として、用意している店舗もあるのではないでしょうか。 人は、新しいものが好きなので、端玉交換の時に奨めると喜んでもらえるかもしれません。 この『晴れ風』は新しいビールというだけでなく、もう一つ新しい試みをしています。 それは「日本の風物詩を守る活動」です。
ビール缶にQRコードがあるのですが、これをスマホで読み取ると動画流れ、 何(例えば桜の木)を守りたいか、キリンからのメッセージが流れます。 そして、方法は2つということで、この『晴れ風』を購入する方法(350ml=0.5円、500ml=0.8円)と、 キリンから配布される0.5円相当のポイントを寄付する方法があると説明してきます。 ポイントは、このサイトを見ると付与されるので、それをどこの自治体に配るかを自分で選びます。 キリンの社会貢献を消費者が一緒に手伝っているという感じです。
社会貢献をしようとしている組織を応援することは、自店の社会貢献につながります。
サービスカウンターで、キリンの『晴れ風』試してみましたか?
味はいかがでしたか?などと尋ねながら、端玉景品の『晴れ風』を紹介し、
同時にこのキリンの取り組みを説明するのも悪くないと思います。
地域密着型ホールやコミュニティホールを目指しているなら、
こういう取り組みをお客様に紹介することで、自店の社会貢献の姿勢をアピールするのもありだと思います。
最後に注意点としては、すでに案内した人に同じ案内をしないようにしてください。 それはあなたとの会話を覚えていないというメッセージになるので、 カウンタースタッフにはその点を注意するように説明する必要があるでしょう。 せっかくの会話で培ったお客様との関係がビールの泡のごとく消えてしまうのはまずいですから・・・。
・・・ 👆目次
作成日:
■春の交通安全運動を応援して地域貢献!
ご存知とは思いますが、昨日6日から春の交通安全運動が始まりました。 今回の運動の重点項目は次の3つです。
○ こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
○ 歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
○ 自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
交通安全運動と言えば、軽微な違反の取り締まり強化というイメージがあるのではないでしょうか。 軽微な違反で捕まった人の中には立腹し、「こそこそと軽微な違反を取り締まるのは、警察のボーナス稼ぎだ!」などという人もいるようです。 しかし、軽微な取り締まりを徹底することが、大きな事故への防止になることは、「割れた窓」理論から推測することができます。 小さな違反の放置が、大きな違反、大きな事故につながります。 地域密着型の店舗としては、地域の人々の安全を守るために、積極的に地域の交通マナーの向上に貢献していくことは大切なことです。 そういう意味では、交通安全運動にはポスターを貼ったり、お客様に声掛けすなど、積極的に参加することが望まれます。
この春の安全運動では、こどもを含む歩行者への安全意識の徹底と、
自電車や電動キックボードなどの免許のいらないモビリティ利用者の交通ルールの徹底です。
警察庁の資料によると時間帯別で子供の事故発生を見ると15時がピークになっています。
お客様には15時から17時は学童の帰宅時間になるということで、特に気を付けるように伝えるのもいいかもしれません。

そして、歩行者優先意識と言えば、信号機のない横断歩道を渡ろうとしている人への対応です。 みなさんはクルマの運転をしていて、信号機のない横断歩道で立っている人を見かけたら止まっていますでしょうか? ちなみに信号機のない横断歩道でクルマが一時停止してくれるかどうかを調査した結果、長野県がダントツの1位となっています。 長野県では横断歩道でクルマが一時停止する率がなんと**72.4%**で、全国平均の21.3%を大きく上回っています。 ネットで調べると5年連続となっていました。 交通安全文化が定着しているのでしょう。

私の住んでいる奈良県は27位で**19.0%**でした。 実を言えば、先月の夕方、自転車を押して横断歩道を押して渡っている60歳過ぎの女性を、バスが轢きそうになったところを目撃しました。 まさかの事故目撃かと思いましたが、大丈夫でした。 女性は慌てて横断歩道を渡り、バスの運転手がにらんでいました。 女性はバスとの距離があったので渡ったので、悪いのはバスの方だと思います。 バスの運転手が誤るどころか睨んでいたのには、少し驚きました。 奈良も交通マナーの向上が必要な地域だと思いました。
さて、みなさんの地域ではいかがだったでしょうか。 こういうデータ数字などを示しながら、店舗で交通安全を呼び掛けて、自地域の交通マナーを改善するのも、地域密着店としての地域貢献になるのではないでしょうか。
・・・ 👆目次
作成日:
■アメックスの新ゴールドカードの刷新を参考にする!
アメックスが新しいゴールドカードを発表したことをご存知ですか? アメックスはご存知のようにクレジット会社です。 VISAやマスターカードと同じ業界ですね。
このアメックスが『ゴールド・プリファード・カード』という新しいゴールドカードを作りました。 ところで、みなさんはゴールドカードをお持ちでしょうか? どこかのクレジット会社のゴールドカードを1枚か2枚は持っているよという方も多いと思います。 実際、いろいろな会社がいろいろなゴールドカードを出しています。 これが今回アメックスが、ゴールドカードを新しくした理由なんですね。
アメックスはゴールドカードが大量に出回っている状況を見て、これはおかしいと感じたようです。 そもそもゴールドカードは一部の上位客に対して発行するものであり、特別性と希少性を有するカードのはずなのですが、 今は誰でもゴールドカードを持っている時代になっている。 正にゴールドカードの大衆化。 ステータスも何もない!? ちなみにNTTドコモ調査によると、ゴールドカードを持っている人の62.8%が年収400万円未満の人になっているようです。

ニュース番組WBSの報道によると、この現実を見てアメックスは、あたらめてゴールドカードの存在意義を考えたそうです。 「ゴールドカードが果たすべき役割とは何か?」 「ゴールドカードに求められる魅力とは何か?」
そして作り上げたのが2月に発表された『ゴールド・プリファード・カード』です。
年会費は3万9,600円(従来より8,000円値上げ)。
カード自体も従来にプラスチックからメタルカードに変えています。
特典としては、例えば国内のプレミアムホテルに無料で宿泊ができたり、
ホテルのダイニングで料理が10~20%割引されるなどです。
カード特典を利用すると年間64,300円相当の価値があるとのことです。
これ以外にもいろいろな特典を用意していますが、基本的にはカード所有者の豊かなハイクラス・ライフスタイルを応援するというものです。
正に本来の”ゴールドカード”という感じになっています。
ここで着目したいのは、アメックスが惰性に任せてカード運営をしていないという点です。 世の中が変化し、従来のサービスが本来と違うものになっていくのを良しとせず、 本来の目的とは何かを問い直し、改善している点です。 パチンコ業界もカードを発行していますが、現在のカードの在り方が最善であるということはありません。 本来自店にふさわしい会員カードとは何かを考え、カードの在り方、特典の在り方を再設計するという考え方があってもいいのではないでしょうか。
・・・ 👆目次
作成日:
■失敗を成功の糧とする企業に学ぶ!
先月和歌山で国産の小型ロケットの発射が失敗に終わりました。 成功すれば日本では民間初のロケット打ち上げの成功となるはずでした。 何かに挑戦しようとすれば失敗はつきものです。
まったく失敗をしない人はいません。
人は挑戦する限り、失敗は免れません。
したがって、全く失敗しない人は挑戦を全くしてない人ということができるのかもしれません。
店舗の運営でも、何か新しい企画をして思った通りの結果が出なかったことがあると思います。
ままあることだと思います。
失敗をした後の対応は大きく2つに分かれます。
1つは失敗をしても再度目標に向かって挑戦する人です。
もう一つは、失敗に懲りて、目標を諦める人です。
会社としては、単純に一度の試みで失敗したとしても、
諦めずに挑戦し続ける人が必要です。
先ほど、小型ロケットの打ち上げ失敗も、これで終わりでは話になりません。
この失敗を乗り越えてもらわなければなりません。
でも、頑張ったからといって、誰もが乗り越えられるとは限りません。
単純にまた新たにロケットを作りました。
また打ち上げますで、成功するでしょうか?
成功も失敗も時の運、何度も挑戦すればそのうち成功する。 確かにそういうこともあるかもしれません。 しかし、あなたがロケットの会社の社長ならどう思うでしょう? 1回の失敗で巨額の赤字です。 新台入替の失敗とは比べモノになりません。 それをそのうち成功するだろうと、安易にロケットを作る担当者をそのままにしておくでしょうか? おそらく自分が社長なら、その担当者は会社を地獄に突き落とす悪魔に見えると思います。
このロケット会社は「スペースワン」という会社です。
再挑戦をすることは確実です。
ではどのような形で再挑戦をしようと考えているのでしょうか。
小型ロケット『カイロス』の打ち上げ失敗の会見の時に豊田正和社長は以下のよう言っています。
「スペースワンとしては、失敗ということがを使いません。
なぜかというと、その中の1つ1つの試みの中に、新しいデータがあり、経験があり、
そうしたものは全て、今後の新しい挑戦に向けての糧と考えています」
要約して言えば、失敗は成功するための不確定要素の明らかしたことであり、
その不確定要素に対応することで、成功のための確率を上げていくプロセスにしか過ぎないということです。
この社長の考えでは、挑戦における失敗は、成功確率を上げるための行為であり、早晩成功を掴むことができるということになります。
そのために挑戦に際しては、あらゆるデータを取ることで、次への足掛かりを作っています。
データがあることで、良かったところと悪かったところを明確にし、悪かったところの改善に取り組んでいける。
だから、やればやるほど(失敗すればするほど)成功に近づいていくという仕組みを取り入れているということです。
どうでしょう。もしみなさんが社長で、部下がこのような感じで失敗を成功の糧にしてくれるなら、安心するのではないでしょうか。
初めから成功するのが最も良いのですが、このような仕組みがあれば、たとえ失敗してもそれは次への投資になるので、光明が見えていると思います。
ところで、みなさんの会社や店舗では、「スペースワン」のような仕組みはできているでしょうか? もし、失敗がタダの無駄になっていると感じるものがあるなら、 豊田正和社長のような考え方を取り入れて仕組みを作ってはいかがでしょうか?
・・・ 👆目次
作成日:
■入社式のニュースを見て、新メンバー教育を考える!
新年度が始まると必ずニュースなるのが入社式です。 コロナが5類に移行したことで、何ら制約を受けることのない入社式を行う様子が紹介されました。
新入社員向けの施策として、私の注意を引いたのが、パナソニックの新入社員に対する家電購入補助制度の発表です。 支給額は最大10万円です。 物価が上昇する中、まだお金を稼いでいない新入社員の生活負担を和らげる施策です。 もちろん、家電のブランドはパナソニックに限るということです。
新入社員がすべてパナソニック家電を使っているかと言えば、そうではないと思います。 実際、パナソニック家電を使ったことがない人も結構いると思います。 でも、この状態はあまり好ましくありません。 やはり会社に愛着を持ってもらうには、自分たちが作っている製品の良さを実感してもらいことから始まります。 なので、この施策は生活応援プラス、自社への愛着、しいては新入社員の定着を促進するものとなります。 加えて、実際自分たちがパナ製品を使用して不都合があるなら、将来の製品改善を提案するきっけにもなります。 一石三鳥の施策ではないでしょうか。
孫子の兵法に「敵を知り、己を知らば、百戦危からず」という言葉があります。 新入社員ですので、まず己(自社)を知ってもらうことから始めているという感じです。 これはパナソニックだけではありません。 ソニーは自社がテーマとする『感動』を肌で感じてもらうために、人気バンド「緑黄色社会」を呼び、入社式でライブの楽しさを新入社員に体感させています。 西武グループは、グループが経営する横浜・八景島シーパラダイスで入社式を行い、イルカやペンギンを使った演出などで、自グループがお客様に提供しているものが何かを体験させています。 キューピーは、自社の農園でのレタスの収穫、看板商品であるマヨネーズ作りを新入社員に体験させています。
ニュース番組WBSの紹介企業で面白かったのは、GAテクノロジーズです。
この会社は不動産投資などのサービスを行う会社ですが、1日に新入社員すべてに10万円を投資軍資金として渡すことをいきなり発表し、
合わせて金融セミナーを行って、その使い方を考えさせています。
新入社員は突然の10万円の支給ということで驚き、感謝していました。
この施策は会社に対するロイヤリティを高めると同時に、資産を運用するお客様の立場の一端を体験することができ、
資産運用という自社の業務を理解するのに大いに役立つと感心しました。
この行為で資産の運用の大切さについての会社の想いを、新入社員だけでなく、この話を聞いたお客様も感じるのではないでしょうか。
新入社員は50人なので、費用は500万円ですが、WBSが取り上げたことで、広告効果だけみても十分あると思います。
まったく上手い施策であると感心しました。
自分の会社、自分の店舗に入ってきた人に、いち早く自社や自店の良さを知ってもらうことが、一緒に頑張って行く上でとても大切なことです。 新卒採用でなくても中途採用でもアルバイト採用でも同じです。 新しい人に何を知って欲しいか、そのための体験とは何なのか、その体験はいつすべきなのか、 パチンコ業界でもすぐに取り組めることはいくらでもあると思います。 みなさんの会社や店舗では、どのような知恵を出されているのでしょうか? そんなことを思いながらニュースを見ていました。
・・・ 👆目次
作成日: